本記事にはプロモーションが含まれています。

「頼まれると断れない」
「断ったら嫌われそうで怖い」
責任感が強く、周囲に気をつかう人ほど断ることに罪悪感を覚えやすいのではないでしょうか。
よかれと思って引き受けても、逆に信頼を損ねたり、自分の評価を落としてしまうことがあります。
仕事を断ることに悩んでいる会社員の方のために、仕事を断る考え方と信頼関係を崩さずにやんわり断る具体的な伝え方をご紹介します。
無理に引き受けしすぎず、自分のパフォーマンスを最大限に発揮できる働き方のヒントになれば幸いです。
断れない心理と事情

仕事を断ることにためらいを感じるのは理由や心理的な背景があります。
実際によくある状況から断れない原因を整理していきます。
申し訳ない気持ちになってしまう
罪悪感や期待に応えたい気持ちは、断る際の大きな壁になっています。
相手への思いやりが強い人ほど感じてしまうかもしれません。
もちろん引き受けることが誠意となることもあります。
でも今応える余裕があるか、少し考えてから回答しても遅くありません。
評価が下がるかもと不安に感じる
上司からの依頼や社内の立場次第では、断ることで評価が下がると考えてしまい、不安になります。
職場の人間関係や上下関係が気になってしまうのは当然のことです。
でも自分の業務が回らなくなり、ミスが増えては本末転倒です。
埋め合わせに手間がかかったり、人手が必要になったり、かえって評価を下げてしまう可能性もないとはいえません。
断ることへの不安は自然ですが、自分の業務や信頼への影響もあわせて考える必要があるといえます。
過去に断って嫌な経験をしたことがある
断ったことで人間関係が悪くなった経験がある人は、トラウマになっているかもしれません。
記憶が想い起こされ、より断れなくなっています。
断ることは悪いという印象が残っているのではないでしょうか。
今、仕事を抱えて身動きがとれない状況なら、断ることは悪ではない考え方を知っておいて損はありません。
仕事を断れないことで発生する問題
仕事を断れない状態が続くと、ただ忙しくなるだけでは済まない問題も発生します。
問題点を整理し、業務やパフォーマンスにどのような影響が出るのかを確認していきましょう。
業務量が増えすぎてミスや納期遅れにつながる
キャパオーバーの状態で仕事を受け続けると、集中力が続かず、結果的にミスや納期の遅れを招く可能性があります。
誰かの期待に応えたつもりが、成果を出せずに評価を落とすといった悪循環にもなりかねません。
本来の業務に集中できず、成果が出づらくなる
自分の担当業務に使うはずの時間が、余計な対応で削られてしまう。
特に仕事量が多く、長期で取り組む業務がある場合、この時間の消耗が大きなロスになります。
ストレスと疲労の蓄積でモチベーションが下がる
断れないまま頼まれ仕事をこなしていると、精神的な疲れが蓄積していきます。
「なんで自分ばかり」となり、モチベーションの低下にもつながりかねません。
信頼を損なわない断る考え方

断るのは悪いというのは思い込みです。
断ることも信頼関係の一部であるという視点で考え方を整理していきましょう。
引き受けないことも誠実さの一つ
全てを引き受けることが誠実とは限りません。
業務状況を踏まえたうえで対応が難しいと判断した場合、難しいと正直に伝えることが必要です。
対応できる範囲を明確に示すことは、責任のある対応といえます。
断れる人は相手を尊重できる人
断ることはわがままではありません。
対応できない理由を明確に伝えることで、相手もスケジュールや仕事のやり方を考え直しやすくなります。
つまり相手の時間や計画を尊重する行動になります。
断るべきタイミングで適切に断ることは、無駄を減らし信頼関係を維持する上でも重要であるといえます。
仕事でやってはいけない断り方
断ること自体は悪いことではありません。
ただし伝え方を間違えると、職場での信頼や人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。
実際に避けたい断り方の例をみていきましょう。
感情的に断ってしまう
「忙しいって言ってるでしょ!」
「無理です!」
など、言いたい気持ちわかります。
でも感情をぶつけてしまうと関係は確実に悪化します。
イライラしていても、冷静に伝えることが職場での関係性と信頼を守る第一歩です。
理由もなく無理と突っぱねる
一言だけで断ると協調性がない、冷たいといった印象を与えてしまいます。
ビジネスでは謝意、理由、配慮の三点セットが基本です。
嘘やごまかしで断る
体調が悪いはまだしも、妻が倒れました的な嘘やごまかしを重ねるのは避けるべき断り方です。
その場はしのげても、いつか発覚して信頼を失う可能性があります。
同じ職場で長く勤める可能性があるなら、しっかりとした断り方を身につけたいところです。
フェードアウトする
返事をせずに放置するのは、トラブルや誤解を招く原因になります。
社外でまったく関わりたくない場合、問題はないかもしれません。
でも同じ会社内ではコミュニケーション能力を疑われてしまうでしょう。
無理や放置は避けるべき断り方といえます。
私が使ってきた断り方の例
ここでは私が実際に使ってきた断り方の具体例をご紹介します。
誰に対して、どんな言い方で伝えるかによって印象が大きく変わったりします。
上司、同僚、後輩など、関係にあわせた断り方を押さえておきましょう。
余計な気まずさを防ぎ、働きやすくなりますよ。
上司への断り方
- 現在進めている案件の都合で、今すぐは難しい状況です。来週でしたら対応可能です
今取り組み中の作業状況を素直に伝えること、余裕ができる目安を提案すること。
これができると波風が立ちませんでした。
そのためにも普段から自分のタスクをしっかり把握しておくことがおすすめです。
もっとも、上司からの指示は業務命令の場合があります。よくよく依頼の背景と内容は確認しておきたいところです。
同僚や後輩への断り方
- 今は自分の仕事に集中したいので申し訳ない。余裕ができれば手伝えると思うけど、他の誰かにお願いできないかな?
私の経験では、謝意と断る意志をはっきりと示したほうがよかったです。
自分の意志を曖昧にすると断りきれなくなることがあります。
ポイントは前向きに断る
仕事を断るときに大切なのは、単なる拒否ではなく、前向きな姿勢を見せることです。
- 時期をずらせば可能などの条件をしめす
- 対応の優先順位を説明して調整する
- 受けた後のリスクを伝えることで相手に納得してもらう
背景や条件を添えて説明することで、相手の納得感は大きく変わります。
拒否ではなく、建設的で前向きな姿勢が信頼を失わない断る工夫といえます。
それでも!どうしても!なんとか手伝って!という場合は、貸しの一つとして対応してもよいかもしれません。
断るスキルは力になる
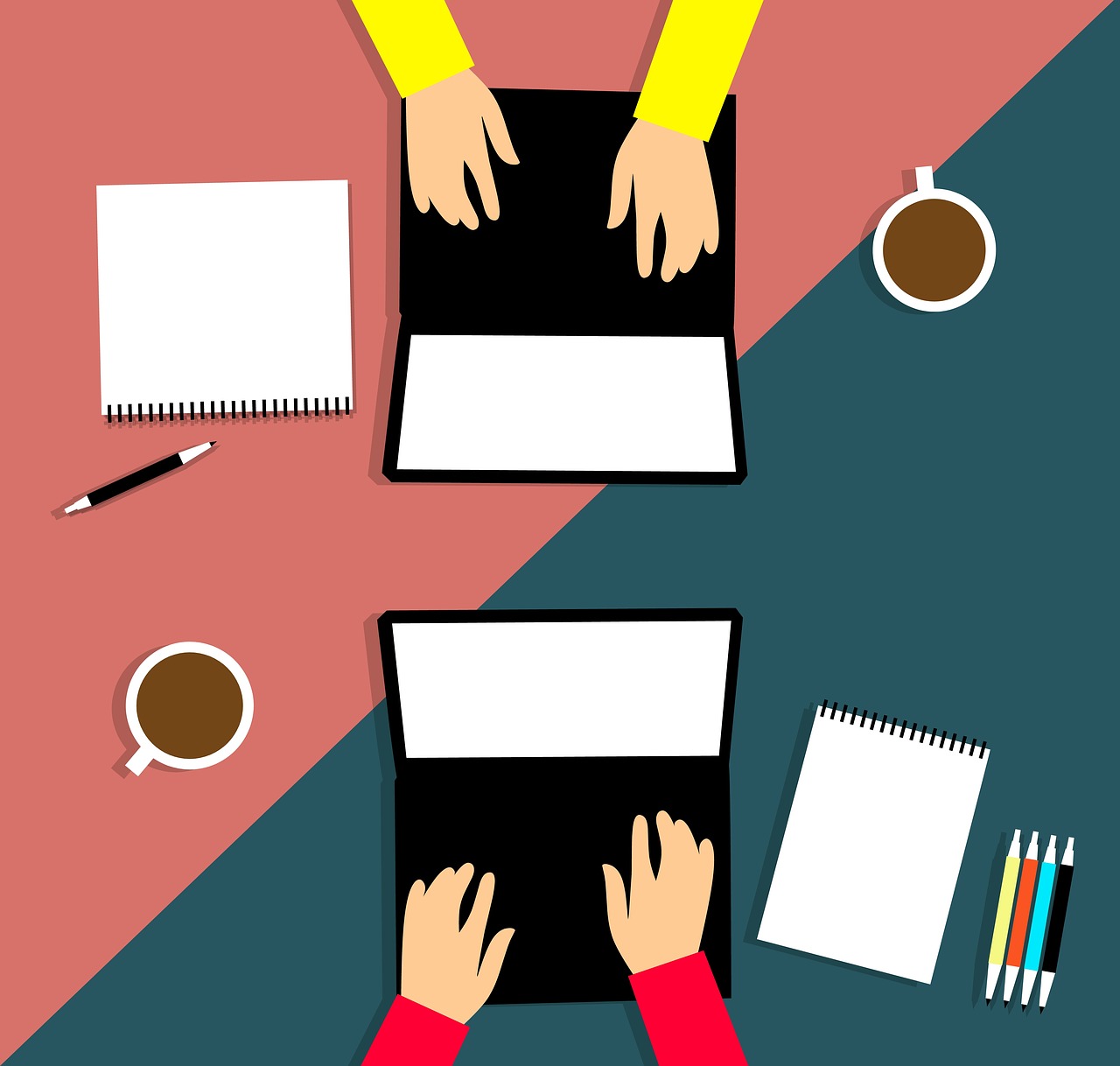
自分の時間と仕事の質を守れるようになる
断ることができるようになると、自分の業務に集中できる環境を整えられるようになります。
人の仕事を手伝うのは、経験や信頼構築になることがあります。
しかし、極論としては直接の自分の成果につながらないことが多いです。
自分の成果につながる仕事に注力するためにも、断り方を実践して身につけておくことがおすすめです。
自分で仕事を選べるようになる
「この仕事はやる」「今はやらない」と判断できることは、働き方の方向性を自分で選べるようになります。
受け身でやらされてる感がなくなるので、仕事が楽しくなってくるかもしれません。
長期的な信頼と評価につながる
断り方が丁寧な人は信用できると思われやすく、結果的に重要な仕事に選ばれる可能性が高まります。
断りきれなかった仕事は自分の糧とする
とはいえ、どうしても断りきれない仕事はあるかと思います。
一度受けた仕事はしっかりこなしつつ、自分の経験や成果として記録を残しておきましょう。
記録することはめんどくさく、おろそかにしがちですが、そこが一番大事です。
データベースやTodoリストなどに残し、後から整理してまとめておきます。
評価の時期が来た時、数字と成果で示せるようにしておくと自分の糧になること間違いありません。
まとめ
断るは申し訳ないことと思い込む必要はありません。
むしろ、きちんと線引きをすることで、相手に誠実さや仕事への責任感が伝わることもあります。
無理に引き受け続けるのではなく自分を守り、関係を丁寧に築いていくための断る力を育てていきましょう。