本ページにはプロモーションが含まれています
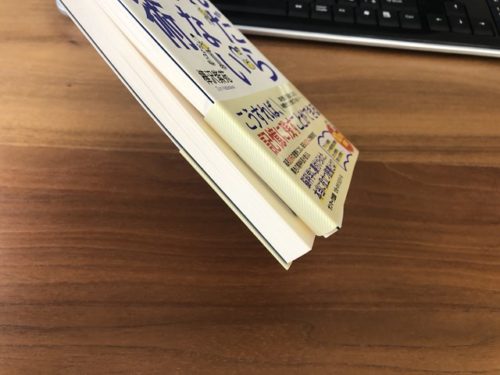
買ってきた本についている「帯」は捨ててしまいますか?
私は「しおり」に利用します。
でも、たまにその「しおり」が外れて読んでいるところがわからなくなります。
その読書方法は間違っているかもしれません。
「読んだら忘れない読書術」を実践すれば、「しおり」が外れたことなどささいな出来事
「しおり」をはさむ、はさまないなどの議論は不毛
本書は精神科医でもあり「アウトプット大全」の著者 樺沢紫苑さんが伝授する読んだら忘れない読書術です。
「せっかく本を読んだのにすぐに忘れてしまう。」
「本の内容を説明しようとしても、どんな内容だったのか説明できない。」
普通にありがちです。
でも解決方法をお探しでしたら本書はおすすめです。
早速読んでみて、手法を一部まとめてみました。
是非読んでみてください。
一部分だけでも1冊の本の有益な情報を忘れず、あますことなく利用できるようになるかと思います。
読んだら忘れないようにするためには
脳は重要な情報以外は忘れる。
では、何をもって「重要な情報」とするのでしょうか。
脳が「重要な情報」と判断する基準は2つです。「何度も利用される情報」と「心が動いた出来事」です。
読んだら忘れない読書術文中より引用
読んだら忘れない読書をするためには、この要素を読書の中に取り入れること。
「では、普段の読書にどんな風にとりいれればよいのだろう?」
樺沢さんが提案する読書術の中で最も印象に残った内容を次項でご紹介します。
具体的な読んだら忘れない読書術の例1
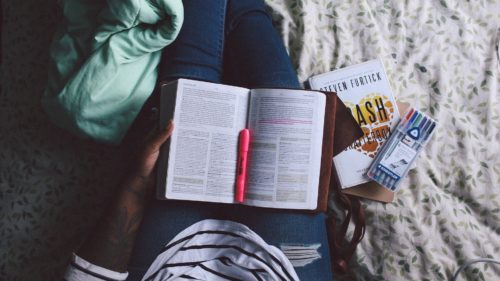
いくつかある読書術で最も重要と感じた読書方法はこれです。
内容が説明できない、議論ができない、読んで感想や自分の意見が述べられないといったことがすべて解消されそうです。
インプットから1週間以内に3回アウトプットする
具体的にはこんなアウトプットがオススメされています。
4つのアウトプットのうち一週間に3つ実行するとやらない時よりはるかに記憶に残るそうです。
①メモを取る、マーカーでラインを引く。
簡単にできそうですね。
ただ、図書館で借りた本にマーカー引いたら怒られそうなので、購入おすすめ。
本書には、より効果的で具体的な方法が紹介されています。
②内容を人に話す。人に勧める。
知人や家族にピンポイントで最も印象に残る、役に立ったと感じたことを要約して説明してみます。
読んだ本が話のタネにもなるのでいいですよね。
聞いた人もある程度内容がわかれば、興味が惹かれるかどうか読む前に判断できるので良いかもしれません。
③感想や気づき、名言をSNSでシェアする。
SNSだと文字数も限られているので、重要に思えたことがピンポイントでアウトプット出来そうです。
④書評、レビューを書く。
書評、レビューは少しハードルが高い気がしますが、書評を書くこと前提で本を読むと気づき量の多さが全然変わってくることに気づきました。
ブログなら1記事分コンテンツを増やせちゃいます。
SNS以外に発信ツールがあるならチャレンジする価値ありです。
【重要】書見台は絶対利用したほうがいい。アウトプットがはかどります。
メモを取るにもレビューを書くにもSNSで発信するにも、本は開いたままで参照しつつ両手は自由にしておきたいですよね。
そこでオススメなのが書見台です。
アウトプットがはかどりますよ。
いくつか書見台を使用してみた結果、カール事務器の書見台が使い勝手がよかったのでレビューしてみました。ぜひこちら↓の記事もご参考ください。
https://oshigoto.hirospa.com/review-of-carl-jimukis-book-stand-which-makes-it-easy-to-turn-pages
具体的な読んだら忘れない読書の例2

さらに興味深い読書方法を紹介します。
本は最初から一字一句読む必要はない。
「そんなことだれがきめたのでしょう?先入観がジャマをしています」と樺沢さんは述べています。
本は、学びや気付きを得る為のものなので、最適な読み方をすればいいのです。
たとえば次の方法です。
本で一番しりたいことは何か目次をみて目星をつけ、「結論」が書かれていそうなところだけ先に読む
わくわくしそうな知的好奇心を先に満たすことで「心が動いた出来事」になって記憶に残ります。
それから深堀したいところ、疑問に感じたところを戻って読みなおすことで深く読み通すことができるようになります。
まとめ
1冊の本から学びや気づきを説明できるようになれば、その内容は記憶に残るようになります。
それが有益な情報を有効に利用できるようになる方法でもあります。
読んだ本の積極的なアウトプット、結論に目星をつけ先読みしていく読書方法などを紹介してみました。
本書では、実践すれば文字を追うことだけにこだわらず、「しおり」など必要なくなる多くの読書術が記載されています。
特に2章から4章に具体的な方法が満載です!
ぜひ、手に取って読んでいただければ、あなたに最適な読書方法が見つかることは間違いありません。
以上、「【書評】しおりは不要「読んだら忘れない読書術」の手法を学ぶ」でした。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
では、また。